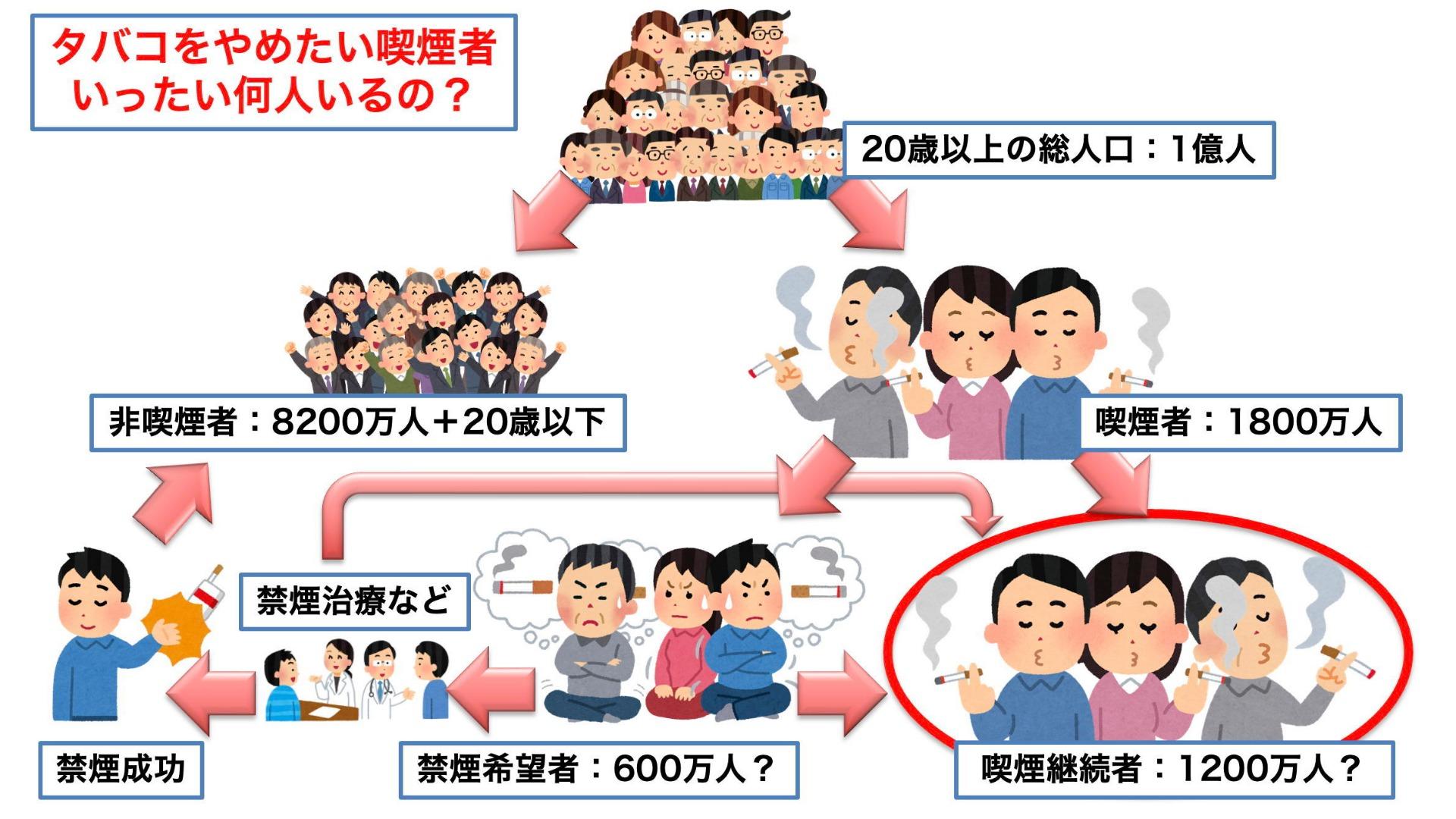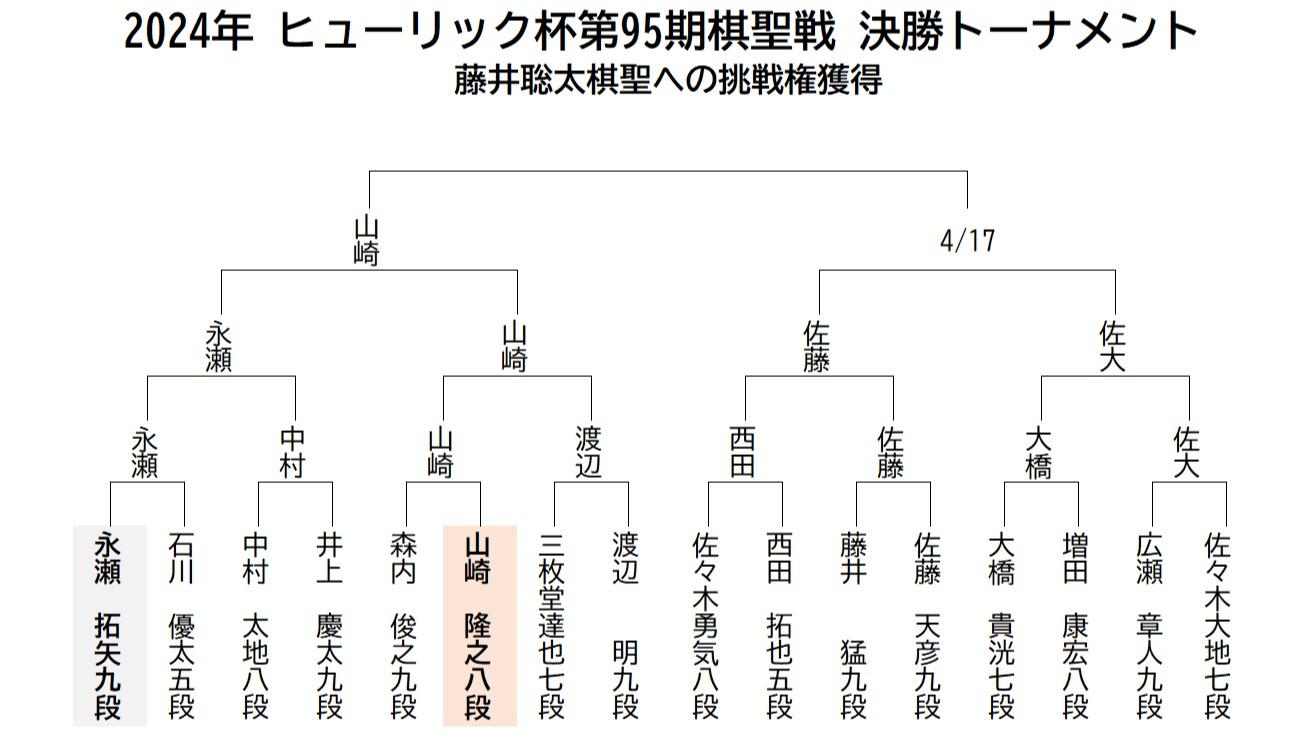外国にルーツを持つ子どもたちの「学ぶ場」が直面する苦境――コロナ禍で支援が先細りに
「常に綱渡りの状況で、子どもたちの学ぶ場所の確保を続けてきました」。外国にルーツを持つ子どもたちが高校進学に向けて学ぶフリースクール、NPO法人多文化共生センター東京。代表理事の枦木(はぜき)典子さんは今、悩んでいる。今年度はコロナ禍の影響で、寄付や助成金が減ることが予測される。しかも、次年度の校舎が確保できず、来年以降も活動を続けられる保証はない。義務教育を終えた後、進学に苦心する子どもたちを救ってきた民間の学び舎。必要とするのはどんな子どもたちなのか。「何から勉強すればいいのか分からず、ひらがなを覚えるのも難しかった。いつも先生の助けが必要です」。そう語る1人の生徒を取材した。
■「たぶんかフリースクール」で学ぶユキオさん
「僕が日本の学校を出て、仕事をして自活すること。それだけが母の願いです」
そう英語で話すユキオ・ダニエル・メシサメンテさんは、フィリピン・ミンダナオ島出身の17歳。彼は6月から、東京・荒川区の町屋駅から路地を入った建物の一角にある「たぶんかフリースクール荒川校」に通っている。
8月、窓を開け、机の間隔を空けた教室で、中国、フィリピン、ウクライナ出身の生徒たち10人余りが学んでいた。彼らは日本語、数学、英語、理科、社会の授業を1日5時間、週4日受けている。
首に巻いたタオルで汗を頻繁に拭うユキオさんは、頭を抱えるように数学の問題を見つめていた。6月にかけ算からスタートした。数学を教える小森律子先生が話す。
「ユキオ君は中学1年生の1学期分をもうすぐ終えます。フィリピンの人は漢字が読めないので、問題文を読むのがとても難しい。彼のいいところは絶対途中の式を書くこと。スピードは遅いけど頑張っている」
ユキオさんは、家に帰るとゲームをするかインスタグラムを見ていることが多いという。短髪でガッチリした体に、スポーツシャツとナイキのスニーカー。趣味はバスケットボールのスポーツ少年だが、日本ではまだ友達が少なく、プレーする機会がない。
■「日本に行けば、素晴らしい未来が待っている」
放課後、ユキオさんと「たぶんか」を卒業したフィリピン出身の高校生らに話を聞いた。フィリピンの若者は仕事を見つけるのが難しいので他の国へ行きたがるという。ユキオさんもこう言う。
「フィリピンでの収入では家族を養えないので、みんな外国へ行くしかない」
17年前、ユキオさんのフィリピン人の母は20代前半で、日本で働いていた。その時に出会った日本人が彼の父だ。母はその後、アラブ首長国連邦でiPhone製造関連の仕事もした。現在ユキオさんの異父姉も同国で働いているという。
2年前、母親に「お父さんがいる日本に行けば、素晴らしい未来が待っている」と説得され、ユキオさんは15歳で母親とともに初来日した。その際生まれて初めて、茨城に住む父と対面した。日本語が全く分からなかったユキオさんは母親の通訳を介して父親とコミュニケーションをとった。父親は母親よりもずっと年上で、病を患っていた。涙を流す父親を見て、ユキオさんは自分も泣きそうだったという。
「日本語を学んで父と話せるようになりたい」
そうユキオさんは言う。一方で、故郷にいる異父妹、祖母、友人たちから離れることがつらく、慣れない異国での生活に不安を感じていた。
■東京へ引っ越してたどり着いた学びの場
ユキオさんは来日後しばらく学校に通えなかった。茨城に住む母親の姉妹の家に母親と落ち着き、中学校に2年生として通い始めた時、来日からすでに4カ月が経っていた。ユキオさんは、学内で唯一、日本語が全く分からない生徒だった。しっかりと日本語指導を受けられる環境はなく、当然他の科目にもついていけなかった。
ユキオさんは中学卒業を控えながらも、高校進学の道が閉ざされていた。その頃、母親が日本人の知人の紹介で「たぶんか」の存在を知った。団体に電話で何度か問い合わせたあと、ユキオさんの次の居場所が決まった。親子は東京・足立区に引っ越し、母は現在、介護士として週に6日働いている。
文部科学省によると、2008年度、公立の小・中・高校等に通い、特別な日本語指導を必要とする児童生徒の数は3万人余りだったが、2018年度には5万人を超えた。NPO法人多文化共生センター東京の枦木典子さんは、背景についてこう指摘する。
「外国籍の人が増えていることが一つの要因。また、子どもが日本語指導を必要としているかどうかは、現場の曖昧な基準で判断されてきた。日本語指導に対する関心の高まりが数字にあらわれている可能性もある」
「たぶんか」は2005年に、西日暮里の2DKのアパートを拠点にスタートした。生徒の多くは、15歳以上の学齢超過の子どもや母国で義務教育を終えて来日した子どもだ。彼らは中学校に通うことができず、自治体は彼らの実態を把握できていない。公的に日本語を学べる場所がない子どもたちだ。
15年間で600人以上が「たぶんか」を卒業し、そのほとんどが高校に進学している。2017年には杉並校も開校。例年は秋にかけて生徒が増え続け、多い年で60人以上が卒業する。今年は入国制限で来日できなかった子どももいたため、10月の時点で生徒数は2校合わせて24人にとどまっている。
■コロナ禍による支援の先細りと、校舎の立ち退き
ユキオさんがやっと辿り着いた学び舎は、以前から財政面で「綱渡り」の状態だった。2014年に文科省の「虹の架け橋教室」という大きな助成が打ち切られた。以降、公的な助成金を出しているのは東京都生活文化局のみ。運営費用の半分を授業料、もう半分を寄付と助成金に頼っている。新型コロナウイルスの感染拡大で経済的打撃を受けた企業からの寄付は、減ることが予測される。
問題はそれだけではない。2018年から校舎として使っている建物が老朽化で解体されるため、今年度いっぱいで立ち退かなくてはならない。だが、移転先はまだ決まっていない。団体は荒川区が無償提供する廃校舎などを転々としてきたが、来年度は区内施設が無償で空く見込みがない。家賃が発生する民間施設への移転は負担が大きい。
家族滞在を伴う在留資格が新たに創設されるなど、今後、外国籍の子どものさらなる増加が予測されている。その一方で「たぶんか」への支援は先細りしていく。枦木さんは現状を憂える。
「『たぶんかフリースクール』が600人を超える卒業生を送り出せたのは、学ぶ場所を安定して確保できているということが非常に大きい。国籍を問わず、学ぶということは子どもが持つ権利。それを保証する視点が行政にも私たち受け入れる側の社会にも必要です」
■「この状況で幸せじゃない人なんている?」
ユキオさんは「たぶんか」について、こう話す。
「何から勉強すればいいのか分からず、ひらがなを覚えるのも難しかった。いつも先生の助けが必要です。『たぶんか』の先生たちが僕にとって初めての日本語の先生。僕を落ち着かせてくれるし、生徒への教え方が好き」
近いうちにユキオさんの母親は、息子に日本国籍を申請させるつもりだ。彼に自分の名前を漢字で書いてもらった。間違った書き順を正すと、彼は嬉しそうに名前を書き直した。「幸男」。彼はこの名前を気に入っている。彼は、母親に支えられ、日本で学び、日本人として働く将来に明るい希望を抱く。「日本での暮らしは『幸せ』?」と尋ねると、ユキオさんはこう答えた。
「この状況で幸せじゃない人なんている?」
日本語がうまくなった時には、父親に母親との馴れ初めなどを聞いてみたいという。
ユキオさんの夢はパイロットか建築家になること。「たぶんか」は今日も彼のような子どもたちの可能性を育てようと奮闘している。社会から「見えない」子どもたちのための「見えない」学び舎を、私たちは見ないようにしていないだろうか。路地裏に一歩足を踏み入れる時のちょっとした勇気。それに似た他者への関心が、私たちに欠けていないだろうか。
クレジット
監督・撮影・編集:岩崎祐